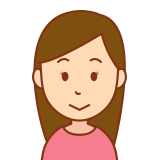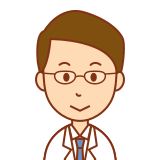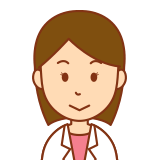愛犬が体をかゆがる、皮膚に赤みや湿疹がある…。
そんな症状に心を痛めている飼い主さんは多いのではないでしょうか。
犬のかゆみや皮膚トラブルの原因はさまざまですが、食事が関係しているケースも少なくありません。
ドッグフードの選び方を中心に、愛犬のかゆみ対策について詳しく解説します。
犬のかゆみの主な原因とは?
愛犬がしきりに体を掻いたり、足を舐め続けていたり、耳をしきりに振っている…。そんな様子を見かけると、「何かの病気かな?」と心配になりますよね。実は、犬の「かゆみ」にはさまざまな原因があります。ここでは、特によく見られる主な原因を紹介します。
1. 食物アレルギー
まず注目したいのが「食べ物」が原因になるケースです。犬も人と同じように、特定の食材に対してアレルギー反応を起こすことがあります。特に多いのが「牛肉」「鶏肉」「乳製品」「小麦」など、ドッグフードによく含まれている食材です。
食物アレルギーによるかゆみは、耳やお腹、足の裏などに症状が出やすく、長引くことが多いのが特徴です。お腹に赤みがあったり、足先を執拗に舐めるような行動が見られたら、食事内容を見直すサインかもしれません。
2. 環境アレルギー(アトピー)
次に多いのが、花粉やハウスダスト、カビ、ダニなど、環境中のアレルゲンによるかゆみです。これは「犬のアトピー性皮膚炎」と呼ばれるもので、遺伝的な要因も関係しているといわれています。
特に春や秋など季節の変わり目に症状が強く出る傾向があります。体の内側(脇の下やお腹など)をかゆがったり、慢性的に耳が赤くなる場合は、このタイプのかゆみを疑ってみましょう。
3. ノミやダニなどの寄生虫
ノミやダニも、かゆみの大きな原因です。特にノミアレルギー性皮膚炎は、たった一匹のノミに刺されただけでも強いかゆみが出ることがあります。
背中から尻尾の付け根にかけてポツポツと赤い湿疹が見られたり、後ろ足で体を激しく掻くような行動があれば、ノミやダニを疑って、すぐに駆虫対策をする必要があります。
4. 皮膚の乾燥やシャンプーの刺激
冬場など空気が乾燥する季節は、犬の皮膚も乾燥してかゆみが出ることがあります。また、合わないシャンプーを使ったり、洗いすぎたりしても、皮膚のバリアが壊れてかゆみにつながることがあります。
特に皮膚が敏感な犬種では、低刺激のシャンプーを使い、洗いすぎないように注意することが大切です。
犬のアトピー性皮膚炎についてのデータ
●荒井延明・薄井志保・纐纈雄三
●スペクトラム ラボ ジャパン(株)
●明治大学農学部
Canine atopic dermatitis(CAD : 犬アトピー性皮膚炎)は,最も頻繁に見られる犬の皮膚疾患である。
日本でのCADの有病率の発表はなく海外でのCADの有病率は10から15%と言われている。人のアトピー性皮膚炎と同様に,CADの発症機構については未解決な部分が多い。
海外では臨床症状と関連因子の解析により複数の診断基準が紹介されているが絶対的なものではなく,CADと確定診断できる検査は存在しない。
犬のアトピー性皮膚炎の発症年齢の調査項目グループ間(犬種以外)での比較
項目 n % 平均(SEM) 統計群 性別 オス 716 30.9 2.49(0.10) a 去勢オス 453 19.5 2.38(0.11) a メス 617 26.6 2.41(0.09) a 避妊済みメス 532 23.0 3.00(0.12) b 飼育者と同じ食事が与えられているか否か 同じもの 986 42.5 2.77(0.09) a 同じでない 1334 57.5 2.41(0.07) b 猫と同居しているか否か 同居している 167 7.2 2.92(0.21) a 同居していない 2152 92.8 2.53(0.05) b 飼育者の喫煙者か否か 喫煙者 1141 49.7 2.43(0.07) b 非喫煙者 1157 50.3 2.69(0.08) a 2,338頭のうち記録がなかったものは含まれていない。a, b グループ内における平均値の異符号間に有意差あり(P<0.05)。
犬のアトピー性皮膚炎の発症年齢の犬種間での比較
犬種 n 犬種% 平均年齢(SEM) 雑種 171 7.4 3.83(0.27) 柴 232 10.0 2.64(0.17) ビーグル 57 2.5 2.67(0.39) プードル 118 5.1 2.16(0.21) パピヨン 48 2.1 2.16(0.38) チワワ 112 4.7 2.06(0.19) フレンチ・ブルドッグ 121 5.2 0.98(0.08) シー・ズー 264 11.4 3.28(0.17) パグ 59 2.5 1.96(0.29) ダックスフンド 298 12.8 2.35(0.12) ウェルシュ・コーギー 61 2.6 2.70(0.25) マルチーズ 48 2.1 3.55(0.52) ミニチュア・シュナウザー 37 1.6 3.17(0.33) シェットランド・シープドッグ 33 1.4 3.67(0.60) アメリカン・コッカー・スパニエル 31 1.3 2.47(0.39) キャバリア・キング・チャールズ・スパニエル 82 3.5 2.17(0.19) ゴールデン・レトリーバー 81 3.5 2.69(0.27) ラブラドール・レトリーバー 79 3.4 2.68(0.32) ウエスト・ハイランド・ホワイト・テリア 54 2.3 2.19(0.32) ジャック・ラッセル・テリア 21 0.9 1.63(0.32) ヨークシャー・テリア 70 3.0 3.08(0.30) ワイアー・フォックス・テリア 30 1.3 2.46(0.37) ボストン・テリア 27 1.2 1.56(0.40) その他 191 8.2 2.11(0.16) 1 (2,338頭-n)は記録がなかった項目。a, b, c, d, e, f 平均値の異符号間に有意差あり(P<0.05)。
食事とアレルギーの関係
〜実は身近な“いつものごはん”が原因かも?〜
愛犬が体をかゆがる様子を見ると、「ノミかな?」「季節のせいかな?」と考えがちですが、意外と見落とされやすいのが「食べ物によるアレルギー」です。
犬の食物アレルギーは、特定の食材が原因で免疫の過剰反応が起き、皮膚のかゆみや炎症、時には下痢や嘔吐など、消化器のトラブルとして現れることもあります。
では、どんな食材がアレルゲンになりやすいのでしょうか?
●よくあるアレルゲン:タンパク質
アレルギーと聞くと、「保存料」や「添加物」が真っ先に思い浮かぶかもしれませんが、実は最も多いのは「タンパク質」なんです。しかも、体に良さそうなイメージのある牛肉や鶏肉、卵、乳製品、小麦など、ふだんよく使われている食材が原因になることが多いのです。
これは、長期間同じタンパク源を摂り続けることで、体が「異物」として反応しやすくなってしまうことがあるためです。
たとえば、鶏肉ベースのフードをずっと食べていた子が、ある日を境にかゆみを訴えるようになった…そんなケースは珍しくありません。
●見落とされがち:人工添加物・保存料
また、人工的な香料や着色料、防腐剤などの添加物も、アレルギーの引き金になることがあります。特に安価なドッグフードには、保存性や嗜好性を高めるためにこうした添加物が多く使われていることがあり、知らないうちに皮膚トラブルの原因になっていることも。
もちろんすべての添加物が悪いわけではありませんが、「なるべく少ない・わかりやすい原材料でできている」フードを選ぶのは、愛犬の健康を守るうえで大切なポイントです。
●にくい症状だからこそ、慎重に
食物アレルギーは、明確な検査でスパッと「これが原因です!」とわかるものばかりではありません。地道な“除去と観察”の繰り返しで、少しずつ原因を絞っていく必要があります。
皮膚に赤みが出る、足先を舐め続ける、耳が赤くなりやすい、便がゆるい…。こうした症状が続くようなら、まず今の食事を見直してみるのも一つの方法です。
ドッグフード選びのポイント
〜“何をあげるか”で、かゆみはグッと変わる〜
愛犬のかゆみが続いていると、「病院に行ったほうがいいのかな」「薬を飲ませた方がいいのかな」と不安になりますよね。でも、まず見直してみてほしいのが「毎日のごはん」です。
人間でもそうですが、口にするものが体をつくっています。犬も同じで、食べるものが皮膚や毛並み、そして体調に大きく影響しているんです。ここでは、かゆみやアレルギーが気になる子のために、ドッグフードを選ぶときの大事なポイントを3つご紹介します。
● 1. 新奇タンパク質(鹿肉・魚など)を取り入れる
「新奇(しんき)タンパク質」という言葉、あまり聞き慣れないかもしれません。これは、「その犬にとって初めて食べるタンパク源」のことを指します。
例えば、鶏肉や牛肉をずっと食べていた子には、それ以外のタンパク源——たとえば鹿肉、馬肉、カンガルー肉、白身魚などが“新奇”にあたります。これらは、過去に体がアレルゲンとして認識していないことが多いため、アレルギー症状が出にくいとされています。
最近では、こうした新奇タンパク質を使ったフードもたくさん出ていて、「なんとなく体調が落ち着いてきた」という声もよく聞きます。
ただし、「何が初めてか」はその子のこれまでの食歴によるので、可能であれば今までに食べてきた食材をメモしておくといいですよ。
● 2. グレインフリーや低アレルゲン設計の重要性
グレインフリーとは、その名の通り「穀物を使っていない」ドッグフードのこと。犬にとって、とうもろこしや小麦、大豆などの穀物は消化しづらいことがあり、アレルギーの原因になってしまうこともあります。
もちろんすべての穀物が悪いというわけではありません。ただ、アレルギーの疑いがある場合は一度グレインフリーのフードを試してみるのも有効な方法です。
また、「低アレルゲン設計」と書かれているフードは、アレルギーが出にくい食材を中心に、シンプルなレシピで作られていることが多いです。原材料を見たときに「聞いたことのある自然な食材」が並んでいれば安心ですね。
● 3. 添加物の少ないものを選ぶ
香料、着色料、保存料…。こうした人工添加物は、見た目や香りを良くするために使われますが、体に負担をかけてしまうことも。とくに皮膚がデリケートな子やアレルギー体質の子にとっては、ちょっとした刺激がかゆみや湿疹のきっかけになることもあります。
「できるだけ素材そのものの力で作られているフード」——それが、添加物の少ないフード選びの基本です。
袋の裏面にある原材料の欄を見て、「〇〇抽出物」「着色料赤〇号」など、あまり見慣れない名前がズラリと並んでいたら、少し注意したほうがいいかもしれません。
犬のかゆみに効く食材とその理由
愛犬が体をかきむしっている姿を見るのって、本当に心が痛みますよね。食べものを少し工夫するだけでも、かゆみを和らげてあげられることがあります。ここでは、毎日のごはんにちょっと加えるだけで皮膚の調子がよくなるかもしれない食材を紹介します。
1. 魚(サーモン、イワシなど)
皮膚の炎症を抑える力あり!
脂ののった魚には「オメガ3脂肪酸」がたっぷり。この成分は、体の中の炎症を抑えてくれるので、アレルギーやかゆみがある子にぴったりです。
缶詰の水煮でもOKですが、塩分無添加のものを選びましょう。もちろん骨は取り除いてくださいね。
2. 亜麻仁油やチアシード
魚が苦手な子にはこちら!
オメガ3は魚だけじゃなく、植物にも含まれています。亜麻仁油(あまにゆ)やチアシードを、普段のごはんにちょっとかけるだけでも効果が期待できます。
ただし、油は酸化しやすいので冷蔵保存をお忘れなく。
3. カボチャやニンジン
ビタミンたっぷりで肌の再生をサポート!
βカロテンやビタミンAが豊富で、皮膚の修復や保湿を助けてくれます。柔らかく煮て、つぶしてごはんに混ぜるのが◎。特に乾燥肌の子にはおすすめです。
4. ブルーベリー
意外かもしれませんが、抗酸化力がすごい!
人間にもいいブルーベリー。犬にも少しならOKです。体の中の「サビ」を防いでくれる抗酸化物質が、皮膚トラブルにもよい働きをしてくれます。冷凍のまま数粒あげるのもOK。
5. 卵(よく火を通して)
皮膚や被毛の栄養源になるタンパク質!
良質なタンパク質とビオチンが皮膚の健康を支えてくれます。ゆで卵やスクランブルエッグにして(味付けなし)、トッピング感覚で。
4. 注目の成分でかゆみ対策
〜薬に頼る前に、“ごはんでできること”〜
犬のかゆみ対策というと、まず思い浮かぶのは薬やシャンプー。でも、実は毎日のごはんの中に、かゆみをやわらげてくれる成分があることをご存知ですか?
ここでは、特に注目されている2つの成分「オメガ3脂肪酸」と「プレバイオティクス」について、わかりやすく解説します。
● オメガ3脂肪酸(EPA・DHA)
〜“皮膚のうるおい”を守る天然のサポーター〜
オメガ3脂肪酸は、青魚などに多く含まれている良質な油のことで、**EPA(エイコサペンタエン酸)とDHA(ドコサヘキサエン酸)**という名前でも知られています。
この成分、実は人間の肌トラブルにもよく使われているもので、炎症を抑える働きがあります。つまり、皮膚が赤くなったり、かゆみが出たりするときに、体の中から穏やかにサポートしてくれるんですね。
特に乾燥しやすい時期や、アレルギー体質の子にとっては、皮膚の“バリア機能”を高めるうえでも心強い存在。フードに最初から配合されているものもあれば、サーモンオイルなどで補う方法もあります。
※オメガ3は時間が経つと酸化しやすいため、保存方法にも少し注意が必要です。
● 腸内環境を整えるプレバイオティクス(例:オリゴ糖)
〜「お腹の元気」は「皮膚の健康」〜
「かゆみと腸?関係あるの?」と思われるかもしれません。でも、腸内環境が乱れると、免疫バランスが崩れて皮膚に不調が出やすくなることがわかっています。
ここで注目したいのが、「プレバイオティクス」という成分。これは、腸内の善玉菌のエサになる食物繊維や糖分のことで、特に有名なのが「オリゴ糖」です。
オリゴ糖は、大腸に届いてビフィズス菌などの善玉菌を元気にし、悪玉菌の増殖を抑えてくれます。その結果、腸内のバランスが整い、免疫力が安定 → アレルギー反応が起こりにくくなるという流れになります。
さらに便通もよくなるので、「かゆみ+お腹の調子がイマイチ」な子には特におすすめです。
フードの切り替え方と注意点
〜焦らず、じっくり。ごはんの変化は小さく始める〜
愛犬のかゆみ対策として、新しいドッグフードを試してみようと思ったとき。すぐに全部変えたくなる気持ち、すごくよく分かります。でも、犬の体はとってもデリケート。いきなりの切り替えは、お腹や体調に負担をかけてしまうことがあるんです。
ここでは、フードをスムーズに切り替える方法と、そのときに気をつけて見ておきたいポイントをご紹介します。
● 新しいフードへの切り替えは“少しずつ”が基本
フードの切り替えは、1〜2週間かけて、ゆっくりと行うのが理想です。
はじめの数日は、新しいフードをほんの少しだけ、今までのごはんに混ぜる程度でOK。そこから少しずつ量を増やしていきます。
以下は、目安のスケジュールです:
| 日数 | 旧フード | 新フード |
|---|---|---|
| 1〜3日目 | 75% | 25% |
| 4〜6日目 | 50% | 50% |
| 7〜9日目 | 25% | 75% |
| 10日目以降 | 0% | 100% |
このペースよりももっとゆっくり進めても構いません。大切なのは、「愛犬の体調に合わせて、無理をしないこと」。急ぎすぎると、下痢や吐き気、かゆみの悪化が起きることもあります。
● 切り替え中にチェックしておきたいポイント
フードを変えるときは、体がどう反応するかをしっかり見ておくことが大事です。特に、以下のような変化がないかチェックしてみてください。
便の状態
形が崩れたり、下痢になっていないか。色やニオイが極端に変わることもあります。
かゆみの変化
フード変更後、かゆみが増えた場合は、アレルゲンが含まれている可能性もあります。逆に落ち着いてきたら、フードが体に合っている証拠かもしれません。
耳・皮膚の状態
耳の赤みや湿り気、皮膚のベタつきや発疹などもチェックポイントです。
食いつき
新しいフードに対して「美味しい」と感じていれば、ストレスも少なく切り替えられます。ただし、味だけで選ばないよう注意です。
おすすめのグレインフリードッグフード
Amarico グレインフリーチキン Healthy Grade RED

Amarico グレインフリーチキン
Healthy Grade RED 成犬用 チキン49.5% ハーブ入り ドッグフード 3kg 全犬種
香料・着色料・合成保存料不使用 穀物不使用 総合栄養食
価格: ¥4,340 (税込)
商品説明
Amaricoチキン49.5%グレインフリーは、無香料・無着色・合成保存料不使用の成犬用総合栄養食です。
穀物の代わりにさつまいもやエンドウ豆を使用し、消化しやすくアレルギーに配慮。
海藻やハーブを配合し、ビタミン・ミネラルを補給。
さらに、グルコサミンとコンドロイチンが関節の健康をサポートします。
Amarico グレインフリーフレッシュチキン Premium Grade GOLD

Amarico グレインフリーフレッシュチキン
Premium Grade GOLD 1歳以上の成犬~シニア犬用 フレッシュチキン36%
香料・着色料・合成保存料不使用 穀物不使用 総合栄養食
価格: ¥5,950 (税込)
商品説明
Amaricoプレミアムグレードは、第一主原料に新鮮な鶏肉36%を使用したグレインフリーの高品質ドッグフードです。
穀物の代わりにエンドウ豆やポテトを使用し、消化しやすくアレルギーに配慮。
ビール酵母(MOS)が腸内環境を整え、免疫力をサポート。
さらに、関節・心臓の健康や体重管理を助ける成分も配合し、愛犬の健康維持に貢献します。
まとめ
ドッグフードを切り替えるときに大切なのは、「早く変えること」ではなく、「愛犬の体にやさしく変えてあげること」です。急な切り替えはお腹を壊したり、体調を崩したりする原因にもなりかねません。
新しいフードは、いつものごはんに少しずつ混ぜながら、1〜2週間かけてゆっくり移行していくのが基本。便の状態やかゆみの変化、食いつきなどを観察しながら、無理のないペースで進めていきましょう。
「この子にはどんな食事が合うのか?」を見つけていくことは、時間がかかるかもしれません。でも、飼い主さんがじっくり向き合うことで、きっと愛犬もその変化を受け入れてくれます。
毎日のごはんが、愛犬の健やかな肌と、笑顔につながるように――そんな気持ちで、まずは一歩踏み出してみてください。
※出典
- 【獣医師監修】犬の皮膚・食物アレルギーにおすすめのドッグフード – ドッグフードの神様
- 【獣医師監修】犬のアレルギーや皮膚トラブル対策におすすめのドッグフード – inunavi
- アレルギー対策のドッグフード11選【獣医師監修】 – こすもす動物診療所
- アレルギー対策におすすめのドッグフード10選!かゆみが減る餌は? – エキサイト
- アレルギー対応のドッグフードに変えるべき?脱毛・かゆみなど皮膚が気になる犬のごはん選び – POCHI
- 犬の皮膚病に良い食事|ドッグフードの選び方やおすすめ商品も紹介 – みらいのドッグフード
- アレルギー対策を考えたドッグフードの選び方!原材料や添加物をチェック – Nature Links
- 愛犬のアレルギーの原因はドッグフード?選び方や出やすい食べ物を解説 – ハピネスダイレクト